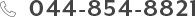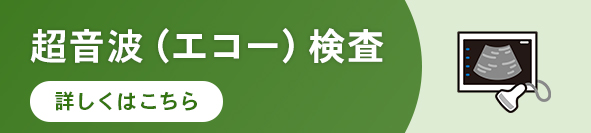各検査の詳細
ヘモグロビン
ヘモグロビンとは
- ヘモグロビンは、赤血球の中に存在するタンパク質の一種で、全身に酸素を運ぶという非常に重要な役割を担っています。肺で吸い込んだ酸素と結びつき、血液の流れに乗って体の隅々まで酸素を届け、同時に二酸化炭素を回収して肺に戻します。
- このヘモグロビンの量が不足すると、酸素を十分に運ぶことができなくなり、貧血を引き起こすことがあります。貧血になると、全身に酸素が行き渡らなくなるため、疲れやすさ、息切れ、動悸、めまいなどの症状が現れます。そのためヘモグロビン値を測定することで、貧血の有無や程度を判断することができます。
正常値
- 男性:13.0~16.9 g/dL
- 女性:11.6~14.8 g/dL
異常値が出た場合に考えられる病気
- 低い場合:鉄欠乏性貧血、再生不良性貧血、溶血性貧血、ビタミンB12欠乏症、葉酸欠乏症、がんなど
- 高い場合:多血症、脱水症状、肺疾患、心疾患など
血清クレアチニン
血清クレアチニン とは
- クレアチニンは、筋肉の活動によって生成される老廃物です。筋肉で作られたクレアチニンは血液中に放出され、腎臓でろ過されて尿として排泄されます。
- 腎臓の機能が低下すると、クレアチニンをうまく排泄することができなくなり、血液中のクレアチニン濃度が上昇します。そのため、血清クレアチニン値を測定することで、腎臓の機能を評価することができます。
- 血清クレアチニン値は、筋肉量や年齢、性別などによっても影響を受けるため、eGFR と合わせて評価することが重要です。
正常値
- 男性:0.6~1.1 mg/dL
- 女性:0.4~0.8 mg/dL
異常値が出た場合に考えられる病気
- 高い場合:腎臓病、脱水症状、筋肉の分解亢進など
- 低い場合:筋肉量が少ないなど
eGFR
eGFRとは
- eGFR(推算糸球体濾過量)は、血液中のクレアチニン値、年齢、性別などから腎臓の機能を推定する指標です。糸球体とは、腎臓にある小さな血管の塊で、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄する役割を担っています。
- eGFR は、この糸球体がどれくらい効率的に血液をろ過しているかを表す数値で、腎臓の機能を評価する上で重要な指標となります。
- eGFR が低下している場合は、腎臓の機能が低下していることを意味し、慢性腎臓病(CKD)などの疑いがあります。
正常値
異常値が出た場合に考えられる病気
- 低い場合:慢性腎臓病(CKD)、急性腎障害、糖尿病性腎症など
尿素窒素
尿素窒素とは
- 尿素窒素は、タンパク質が分解される過程で生じる老廃物です。体内で生成された尿素窒素は、血液によって腎臓に運ばれ、尿として排泄されます。
- 腎臓の機能が低下すると、尿素窒素をうまく排泄することができなくなり、血液中の尿素窒素濃度が上昇します。そのため、血清クレアチニン値と同様に、尿素窒素値を測定することで腎臓の機能を評価することができます。
- ただし、尿素窒素値は、食事の内容や水分摂取量、肝機能などによっても影響を受けるため、他の検査結果と合わせて総合的に判断する必要があります。
正常値
異常値が出た場合に考えられる病気
- 高い場合:腎臓病、脱水症状、心不全、消化管出血など
- 低い場合:肝臓病など
尿酸値
尿酸値とは
- 尿酸は、細胞の核酸が分解される過程で生じる老廃物です。ほとんどの尿酸は腎臓でろ過され、尿として排泄されますが、一部は体内に残ります。
- 血液中の尿酸値が高くなると、尿酸が結晶化して関節に沈着し、激しい痛みを引き起こすことがあります。これが痛風発作です。
- 尿酸値は、遺伝的な要因、食生活、生活習慣、 certainな病気などによって影響を受けます。高尿酸血症は、痛風だけでなく、腎臓病、心血管疾患などのリスクを高めることも知られています。
正常値
- 男性:3.0~7.0 mg/dL
- 女性:2.0~6.0 mg/dL
異常値が出た場合に考えられる病気
- 高い場合:痛風、高尿酸血症、腎臓病、肥満、メタボリックシンドロームなど
尿蛋白
尿蛋白とは
- 尿蛋白とは、尿の中にタンパク質が検出される状態のことです。
- 健康な人の尿には、通常、タンパク質はほとんど含まれていません。これは、腎臓にある糸球体というフィルターが、血液中のタンパク質をろ過する働きを持っているためです。
- しかし、様々な原因によって糸球体がダメージを受けると、このフィルター機能が低下し、タンパク質が尿中に漏れ出てしまうことがあります。
- 尿蛋白が陽性となる原因は様々ですが、多くは腎臓の病気と関連しています。腎臓病以外にも、発熱、激しい運動、脱水症状などによっても一時的に尿蛋白が陽性となることがあります。
評価基準
異常値が出た場合に考えられる病気
- 腎臓病、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、高血圧、膠原病など
尿糖
尿糖とは
- 尿糖とは、尿の中に糖(ブドウ糖)が検出される状態のことです。
- 通常、血液中のブドウ糖は腎臓でろ過されますが、再吸収されて血液に戻ります。これは、ブドウ糖が体にとって重要なエネルギー源であるためです。
- しかし、血液中のブドウ糖濃度が非常に高くなると、腎臓で再吸収しきれなくなり、ブドウ糖が尿中に漏れ出てしまいます。
- 尿糖が陽性となる原因で最も多いのは糖尿病です。 糖尿病では、インスリンというホルモンの作用不足などにより、血液中のブドウ糖濃度が高くなります。
評価基準
異常値が出た場合に考えられる病気
- 糖尿病、妊娠糖尿病、甲状腺機能亢進症、クッシング症候群など
HbA1c(ヘモグロビンA1c)
HbA1c(ヘモグロビンA1c)とは
- HbA1c(ヘモグロビンA1c)は、過去1~2ヶ月の平均的な血糖値を反映する指標です。
- 赤血球中のヘモグロビンは、血液中のブドウ糖と結合する性質があります。HbA1cは、このブドウ糖と結合したヘモグロビンの割合を示すものです。
- 血糖値が高い状態が続くと、HbA1cの値も高くなります。HbA1cは、糖尿病の診断や治療効果の判定に広く用いられています。
- 従来の血糖値検査では、採血時の血糖値しか測定できませんでしたが、HbA1cを測定することで、より長期的な血糖コントロールの状態を把握することができます。
正常値と予備軍
- 4.6~5.2%:正常
- 5.3~6.4%:糖尿病予備軍
- 6.5%以上:糖尿病型
異常値が出た場合に考えられる病気
血糖値
血糖値とは
- 血糖値とは、血液中のブドウ糖の濃度のことです。
- ブドウ糖は、体にとって重要なエネルギー源です。食事によって摂取されたブドウ糖は、血液中に吸収され、全身の細胞に運ばれてエネルギーとして利用されます。
- 血糖値は、インスリンなどのホルモンによって調節されています。インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞に取り込む働きがあり、血糖値を下げる効果があります。
- 血糖値が慢性的に高い状態が続くと、網膜症、腎症、神経障害などのリスクが高まります。
正常値
- 空腹時血糖値:70~109 mg/dL
- 食後2時間血糖値:140 mg/dL未満
異常値が出た場合に考えられる病気
- 高い場合:糖尿病、ストレス、ホルモン異常など
- 低い場合:低血糖症、インスリノーマ、ホルモン異常など
HDL-コレステロール
HDL-コレステロール とは
- HDL-コレステロールは、「善玉コレステロール」とも呼ばれ、動脈硬化を予防する働きがあります。
- コレステロールには、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)とHDLコレステロール(善玉コレステロール)の2種類があります。 LDLコレステロールは、血管壁にコレステロールを蓄積させて動脈硬化を促進するのに対し、HDLコレステロールは、血管壁に蓄積したコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあります。
- HDLコレステロール値が高いほど、動脈硬化のリスクが低くなるといわれています。
正常値
- 男性:40 mg/dL以上
- 女性:50 mg/dL以上
異常値が出た場合に考えられる病気
- 低い場合:動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などのリスク増加
LDL-コレステロール
LDL-コレステロールとは
- LDL-コレステロールは、「悪玉コレステロール」とも呼ばれ、動脈硬化を促進する働きがあります。
- LDLコレステロールは、血管壁にコレステロールを運び、蓄積させる働きがあります。LDLコレステロール値が高い状態が続くと、血管壁が厚くなり、血管が硬くなってしまいます。これが動脈硬化です。
- 動脈硬化は、心筋梗塞や脳梗塞などの深刻な病気を引き起こす原因となります。
正常値
異常値が出た場合に考えられる病気
- 高い場合:動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などのリスク増加
中性脂肪
中性脂肪とは
- 中性脂肪(トリグリセリド)は、体内に蓄えられる脂肪の一種です。
- 食事から摂取したエネルギーが余ると、中性脂肪として体内に蓄えられます。中性脂肪は、皮下脂肪や内臓脂肪として蓄積され、エネルギー源として利用されます。
- しかし、中性脂肪値が高い状態が続くと、動脈硬化などのリスクが高まり脳梗塞や心筋梗塞などの命に関わる病気にかかる可能性が高くなります。
正常値
異常値が出た場合に考えられる病気
- 高い場合:動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などのリスク増加
BNP
BNPとは
- BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)は、心臓から分泌されるホルモンの一種です。
- 心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役割を担っています。しかし、心臓に負担がかかると、心臓の筋肉が stretchedされたり、心臓の内圧が上昇したりします。このような状態になると、心臓はBNPを分泌します。
- BNPは、心臓の負担を反映する指標として、心不全の診断や重症度判定に用いられます。BNP値が高いほど、心臓に負担がかかっていることを示唆します。
正常値
異常値が出た場合に考えられる病気
AST(GOT)/ALT(GPT)
AST(GOT)/ALT(GPT)とは
- AST(GOT)とALT(GPT)は、主に肝臓に存在する酵素です。
- 肝臓は、代謝、解毒、胆汁の生成など、様々な働きを担う重要な臓器です。しかし、肝臓の細胞がダメージを受けると、ASTやALTが血液中に漏れ出てきます。
- ASTやALTの値が高い場合は、肝臓の細胞がダメージを受けていることを示唆し、肝炎、肝硬変、脂肪肝などの疑いがあります。
正常値
- AST(GOT):10~40 U/L
- ALT(GPT):7~40 U/L
異常値が出た場合に考えられる病気
- 高い場合:肝炎、肝硬変、脂肪肝、アルコール性肝障害、薬剤性肝障害など
γ-GTP
γ-GTP とは
- γ-GTPは、主に肝臓や胆道に存在する酵素です。
- γ-GTPは、アルコールの摂取や胆道系の病気で上昇することがあります。γ-GTP値が高い場合は、アルコール性肝障害、脂肪肝、胆石、胆道炎などの疑いがあります。
正常値
異常値が出た場合に考えられる病気
- 高い場合:アルコール性肝障害、脂肪肝、胆石、胆道炎など
腫瘍マーカー
腫瘍マーカーとは
- 腫瘍マーカーは、がん細胞が産生する物質です。
- がん細胞は、正常な細胞とは異なる物質を産生することがあります。これらの物質を腫瘍マーカーと呼びます。腫瘍マーカーは、血液検査で測定することができます。
- 腫瘍マーカーは、がんの早期発見や診断、治療効果の判定などに用いられます。しかし、腫瘍マーカーは、がん以外の病気で上昇することもあります。
正常値
異常値が出た場合に考えられる病気
- CEA:大腸がん、肺がん、胃がん、乳がんなど
- CA19-9:膵臓がん、胆道がん、胃がん、大腸がんなど
- p53:様々ながん
- SCC:子宮頸がん、肺がん、食道がんなど
- シフラ:肝臓がん
- AFP:肝臓がん、精巣腫瘍など
- PIVKA-II:肝臓がん
- エラスターゼ1:膵臓がん